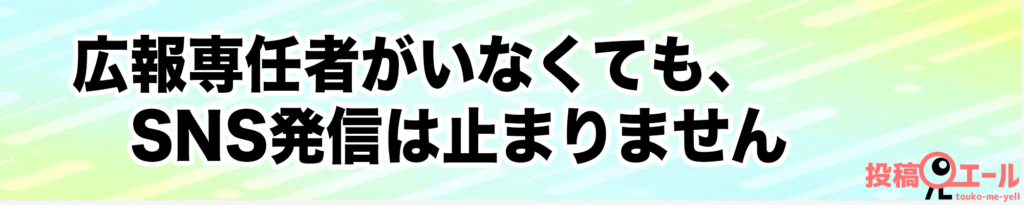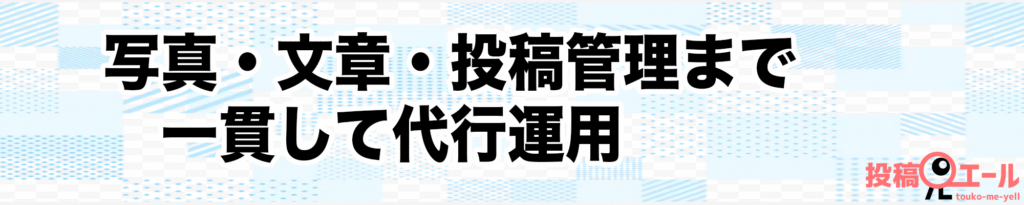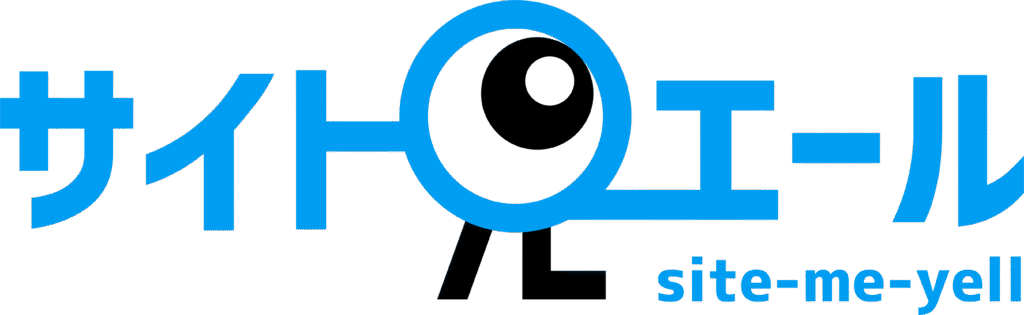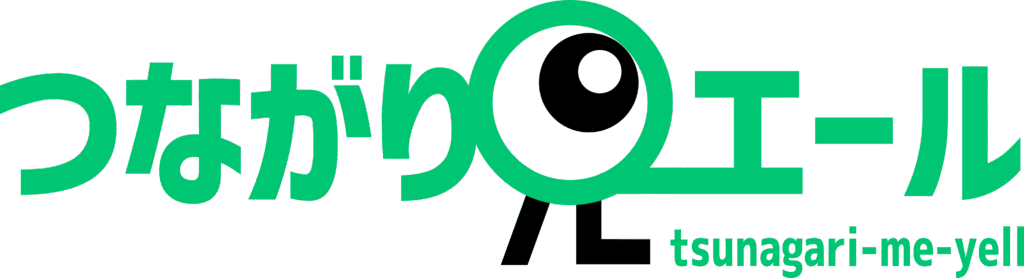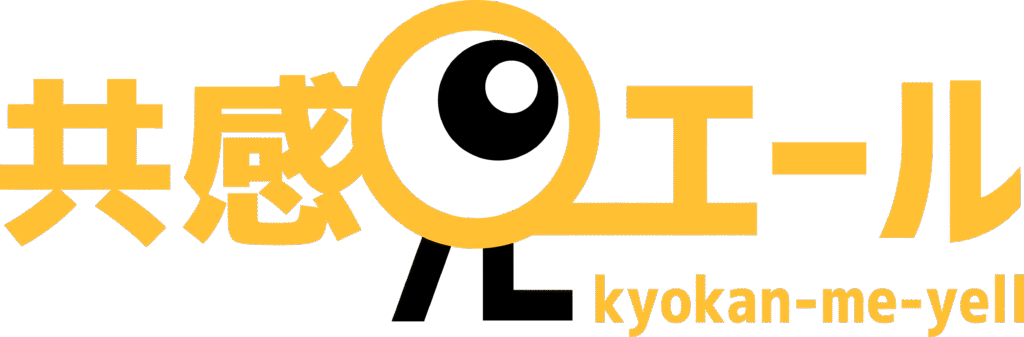この記事は、企業やブランドのSNS担当者、マーケティング担当者、広報担当者など「SNSでフォロワーがなかなか増えない」と悩む方に向けて書かれています。Instagram、X(旧Twitter)、Facebookなど主要SNSの最新アルゴリズムや、2025年の運用トレンドを踏まえ、なぜフォロワーが増えないのか、その本質的な原因と具体的な改善策を徹底解説します。「投稿頻度を上げても伸びない」「ハッシュタグを増やしても効果がない」「エンゲージメントが低い」など、よくある悩みの根本に迫り、明日から実践できるノウハウをまとめました。企業アカウントが陥りがちな“7つの落とし穴”や、SNSごとの伸び悩みポイント、成果を出すための改善プロセスまで、保存版としてご活用いただける内容です。
なぜ今、企業SNSでフォロワーが増えにくくなっているのか
近年、企業SNSアカウントのフォロワー獲得が難しくなっている背景には、SNSプラットフォームのアルゴリズム進化やユーザー行動の変化があります。かつては「投稿頻度」や「フォロワー数」だけで伸びていた時代もありましたが、2025年現在は“質”や“信頼性”が重視される時代へとシフトしています。また、SNSの目的自体も「認知拡大」から「ファン化・信頼形成」へと変化し、単なる情報発信だけではフォロワーが増えにくい構造になっています。この章では、なぜ今フォロワーが増えにくいのか、その全体像を解説します。
InstagramやX(旧Twitter)、Facebookなど主要SNSは、2024年から2025年にかけてアルゴリズムを大きくアップデートしています。これにより、単なる投稿数やハッシュタグの多用ではリーチが伸びにくくなり、ユーザーの興味・関心に合った“質の高い投稿”が優先的に表示される仕組みへと変化しました。特にInstagramでは、保存率やシェア率、Xではリプライや引用リツイートなど、エンゲージメントの“質”が評価指標となっています。今後は「誰に、どんな価値を届けるか」がより重要視される時代です。
- アルゴリズムは“質”重視に進化
- エンゲージメントの内容が評価対象
- 単なる投稿数やハッシュタグ乱用は逆効果
かつては「毎日投稿すればフォロワーが増える」と言われていましたが、2025年のSNS運用では通用しません。アルゴリズムは“ユーザーの反応”を重視するため、内容が薄い投稿を頻繁に行うと、逆にリーチが下がるリスクもあります。また、投稿頻度を上げすぎると、ユーザーのタイムラインで“ノイズ”と認識され、フォロー解除やミュートの原因にもなります。重要なのは「投稿の質」と「ユーザーとの接点」を意識した運用です。
- 投稿頻度だけではリーチが伸びない
- 内容が薄いと逆効果になる場合も
- ユーザーの反応を重視した運用が必須
従来のSNS運用は「多くの人に知ってもらう=認知拡大」が主な目的でしたが、2025年現在は「信頼形成」や「ファン化」が重視されています。ユーザーは情報の真偽や発信者の信頼性を厳しく見るようになり、単なる宣伝や一方通行の発信ではフォロワーが増えにくい傾向です。企業アカウントは、ユーザーとの双方向コミュニケーションや、共感・信頼を得るためのストーリー性ある投稿が求められています。この変化を理解し、運用方針を見直すことが重要です。
- 認知拡大から信頼形成へシフト
- 双方向コミュニケーションが重要
- ストーリー性や共感がフォロワー増加の鍵
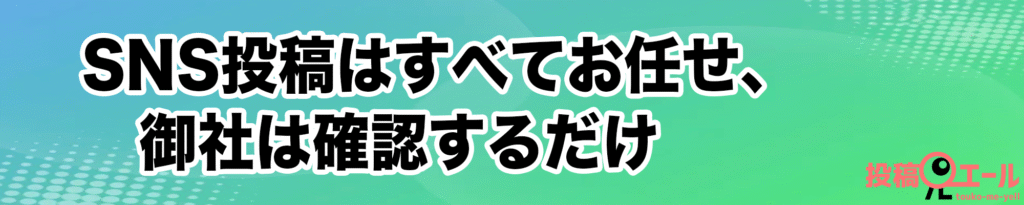
フォロワーが増えない企業アカウントの“7つの落とし穴”
多くの企業アカウントがフォロワー増加に苦戦する背景には、共通する“7つの落とし穴”があります。
これらは、投稿内容や運用体制、分析指標の選定ミスなど、運用の根本に関わる問題です。
ここでは、具体的な失敗パターンとその改善ポイントを詳しく解説します。
自社アカウントの現状と照らし合わせて、どこに課題があるのかをチェックしましょう。
フォロワーが増えない最大の原因は、投稿内容がターゲットユーザーの関心や悩みとズレていることです。自社の伝えたいことばかりを発信していませんか?ユーザーが「役立つ」「面白い」「共感できる」と感じる内容でなければ、エンゲージメントもリーチも伸びません。ターゲットのペルソナを明確にし、ユーザー目線でコンテンツを設計することが重要です。
- 自社目線の発信が多い
- ユーザーの悩みや関心を無視している
- ペルソナ設計が曖昧
ハッシュタグを大量に付ければリーチが伸びる、という時代は終わりました。2025年のアルゴリズムでは、関連性の低いハッシュタグや過剰な数のハッシュタグは、スパム判定やリーチ低下の原因となります。特にX(旧Twitter)では、3個以上のハッシュタグでエンゲージメントが大幅に下がるというデータも。「量」より「質」を重視し、ターゲットに刺さるハッシュタグ選定が重要です。
| プラットフォーム | 推奨ハッシュタグ数 | NG例 | OK例 |
|---|---|---|---|
| 3〜5個 | #人気 #フォロー #いいね | #業界名 #悩みキーワード #地域名 | |
| X(旧Twitter) | 1〜2個 | #トレンド乱用 #無関係タグ | #自社サービス #業界トピック |
どんなに良い投稿でも、ユーザーがアクティブな時間帯に発信しなければリーチは伸びません。各SNSには“アルゴリズムのピークタイム”が存在し、その時間帯に投稿することでエンゲージメントが大きく変わります。自社のフォロワーが最も活動している時間を分析し、最適な投稿タイミングを見極めましょう。曜日や季節によっても変動するため、定期的な見直しが必要です。
| SNS | おすすめ投稿時間帯 |
|---|---|
| 平日19〜21時、土日10〜12時 | |
| X(旧Twitter) | 平日7〜9時、12〜13時、20〜22時 |
| 平日12〜13時、18〜20時 |
投稿ごとに画像や動画のテイストがバラバラだと、アカウント全体のブランドイメージが定着しません。ユーザーは一目で「この投稿はあの企業だ」と認識できる統一感を求めています。色使いやフォント、ロゴの配置、動画の編集スタイルなど、ビジュアル面での一貫性を持たせることで、ブランドの信頼感や親しみやすさが向上し、フォローされやすくなります。ブランドガイドラインを作成し、全投稿で徹底しましょう。
- 画像・動画のトーンが毎回違う
- ブランドカラーやロゴが統一されていない
- 投稿全体の世界観が伝わらない
ユーザーからのコメントやメンション、DMに対する返信が遅い、または無反応だと、せっかくのエンゲージメント機会を逃してしまいます。アルゴリズムは「双方向のやり取り」を重視しており、リアクションが早いほど投稿の評価が上がりやすい傾向です。コメントや質問にはできるだけ早く、丁寧に対応し、ユーザーとの距離を縮めましょう。これがファン化やフォロワー増加の大きなポイントです。
- コメント・DMの返信が遅い
- ユーザーの声に無反応
- エンゲージメントの機会損失
フォロワー数だけをKPIにしていると、運用の本質を見失いがちです。リーチ率やエンゲージメント率、保存率、シェア数など、複数の指標をバランスよく分析することで、アカウントの本当の成長ポイントが見えてきます。特に2025年のSNS運用では「どれだけ深くユーザーとつながれているか」が重要視されているため、指標の再定義が不可欠です。
- フォロワー数だけを追いかけている
- リーチや保存率を見ていない
- 本質的な改善につながらない
SNS運用が一部の担当者に依存していると、ノウハウが蓄積されず、改善サイクルも回りません。属人的な運用は、担当者の異動や退職で一気にクオリティが下がるリスクもあります。チームで運用体制を整え、定期的な振り返りやナレッジ共有を行うことで、継続的な改善と成果につながります。運用マニュアルやガイドラインの整備も重要です。
- 担当者任せで属人的
- 運用ノウハウが共有されていない
- 改善サイクルが機能していない
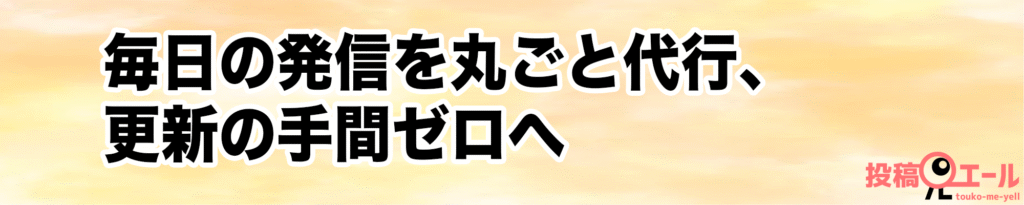
主要SNSごとの“伸び悩みポイント”を整理
各SNSには独自のアルゴリズムやユーザー特性があり、伸び悩みの原因も異なります。Instagram、X(旧Twitter)、Facebook、TikTokそれぞれの特徴と、よくある失敗ポイントを整理し、改善のヒントを解説します。自社アカウントの運用方針を見直す際の参考にしてください。
Instagramでリーチ率が伸びない場合、まず「投稿の保存率」「ハッシュタグの最適化」「ストーリーズやリールの活用」の3点を見直しましょう。保存率が高い投稿はアルゴリズムで優遇されやすく、リールやストーリーズは新規ユーザーへのリーチ拡大に有効です。また、ハッシュタグは関連性の高いものを厳選し、ターゲット層に届く設計が重要です。
- 保存率の高い投稿を増やす
- ハッシュタグは3〜5個に厳選
- リール・ストーリーズで新規リーチ拡大
X(旧Twitter)では、共感や会話を生む投稿がリーチ拡大のカギです。一方的な情報発信ではなく、ユーザーの意見を引き出す質問型ツイートや、時事ネタ・トレンドを絡めた投稿が効果的です。また、リプライや引用リツイートでの双方向コミュニケーションを積極的に行い、エンゲージメントの質を高めましょう。ハッシュタグは1〜2個に絞り、乱用は避けてください。
- 質問型・共感型の投稿を増やす
- トレンドや時事ネタを活用
- リプライ・引用リツイートで会話を促進
Facebookでは、動画やライブ配信、長文のストーリーテリング投稿がアルゴリズムで優遇されやすい傾向です。特にライブ配信はリアルタイムでのエンゲージメントが高く、リーチ拡大に直結します。また、コミュニティグループでの活動や、ユーザー参加型の投稿も効果的です。画像だけの投稿やリンクシェアのみではリーチが伸びにくいので注意しましょう。
- 動画・ライブ配信を活用
- ストーリーテリングで共感を得る
- コミュニティグループでの交流を強化
TikTokでは、動画の冒頭1秒でユーザーの興味を引けるかどうかが勝負です。最初の数秒で「続きを見たい」と思わせる工夫がないと、すぐにスワイプされてしまい、リーチも伸びません。タイトルテロップやインパクトのある映像、音楽の使い方など、1秒目の“掴み”を徹底的に磨きましょう。また、トレンド音源やチャレンジ企画も積極的に取り入れると効果的です。
- 冒頭1秒で興味を引く演出
- タイトルテロップや音楽の活用
- トレンド企画への参加
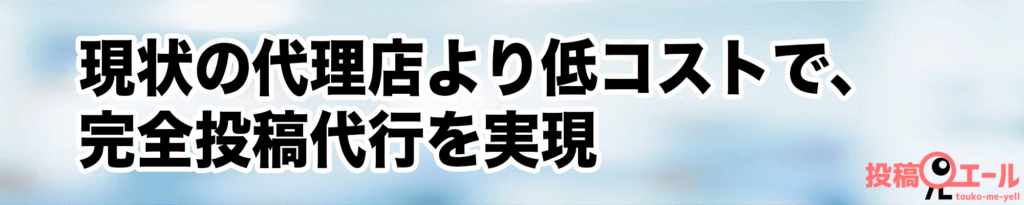
改善の第一歩は「投稿の目的」と「計測指標」の再定義
フォロワーが増えないと悩む企業アカウントの多くは、投稿の目的や計測指標が曖昧なまま運用を続けてしまっています。
まずは「なぜこの投稿をするのか」「どんな成果を目指すのか」を明確にし、それに合ったKPI(重要指標)を設定しましょう。
フォロワー数だけでなく、リーチ率や保存率、UGC(ユーザー生成コンテンツ)反応率など、多角的な視点で成果を測ることが、次の成長につながります。
- 投稿の目的を明確にする
- 複数の指標で成果を評価
- KPIを定期的に見直す
2025年のSNS運用では、単なるフォロワー数よりも「どれだけ多くの人に届いたか(リーチ率)」「どれだけ保存されたか(保存率)」「ユーザーがどれだけ自発的に反応したか(UGC反応率)」が重要な指標となっています。これらの数値を定期的にチェックし、投稿ごとの傾向を分析することで、より効果的な運用が可能になります。特に保存率やUGC反応率は、アルゴリズム上も評価されやすいポイントです。
| 指標 | 意味 | 重要性 |
|---|---|---|
| リーチ率 | 投稿が届いたユーザーの割合 | 新規層への拡散力を測る |
| 保存率 | 投稿が保存された割合 | 有益性・再訪問意欲の指標 |
| UGC反応率 | ユーザー生成コンテンツの発生率 | ファン化・拡散力の証明 |
エンゲージメント(いいね、コメント、シェア、保存など)は、単なる数値ではなく「ユーザーとの接点」として捉えることが大切です。どの投稿でどんな反応が多かったのか、どの時間帯や内容がユーザーの心を動かしたのかを分析し、次の施策に活かしましょう。エンゲージメントの質を高めることで、アルゴリズムからの評価も上がり、自然とフォロワー増加につながります。
- エンゲージメントは“人との接点”
- 反応の質を重視する
- 分析結果を次の投稿に反映
投稿ごとに「認知拡大」「共感獲得」「行動促進(問い合わせ・購入など)」のどれを狙うのかを明確にし、それぞれに合ったKPIを設定しましょう。例えば認知拡大ならリーチ数やインプレッション、共感獲得ならコメント数やシェア数、行動促進ならリンククリックやCV数などが指標となります。目的に応じて投稿内容やクリエイティブも最適化することが、成果につながる運用のコツです。
| 目的 | 主なKPI | 投稿例 |
|---|---|---|
| 認知拡大 | リーチ数、インプレッション | 新商品紹介、キャンペーン告知 |
| 共感獲得 | コメント数、シェア数 | ストーリー投稿、ユーザー参加型企画 |
| 行動促進 | リンククリック、CV数 | クーポン配布、イベント告知 |
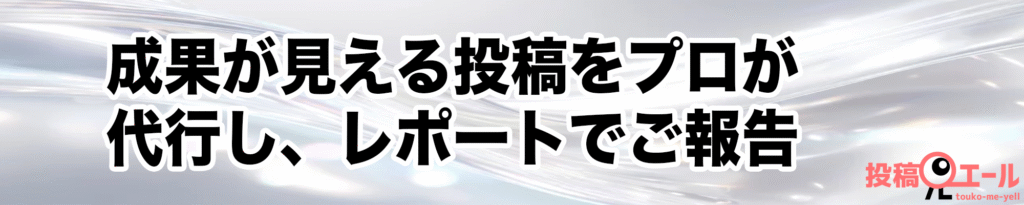
成果を出す企業が実践している改善プロセス
成果を出している企業アカウントは、単発の施策ではなく「継続的な改善サイクル」を徹底しています。投稿ごとのPDCA(計画・実行・評価・改善)を回し、データをもとに仮説検証を繰り返すことで、着実にフォロワーやエンゲージメントを伸ばしています。ここでは、実際に成果を出している企業が実践している改善プロセスを紹介します。
- PDCAサイクルを定期的に回す
- データ分析を習慣化
- チームでナレッジ共有
毎月、投稿内容や反応を振り返り、次月の改善点を明確にするPDCAサイクルを回しましょう。計画(Plan)→実行(Do)→評価(Check)→改善(Action)の流れを定着させることで、運用の質が着実に向上します。特に「評価」と「改善」をチームで共有し、全員で課題意識を持つことが重要です。
- 月次でPDCAを回す
- 振り返り会議を実施
- 改善点を次の投稿に反映
GoogleアナリティクスやSNS専用の分析ツールを活用し、投稿ごとのリーチ率やエンゲージメント率、保存率などを可視化しましょう。データをグラフや表で見える化することで、どの投稿が効果的だったのか一目で把握できます。分析結果をもとに、次の投稿内容やタイミングを最適化することが、成果を出すための近道です。
- 分析ツールでデータを可視化
- 投稿ごとの傾向を把握
- データに基づく改善を徹底
SNS運用は一人で抱え込まず、チーム全体でナレッジや課題を共有することが大切です。定例ミーティングやチャットツールを活用し、気づきや改善点をリアルタイムで共有しましょう。「気づいたらすぐ改善する」スピード感のある文化を作ることで、運用の質が大きく向上します。
- チームでナレッジ共有
- 改善点を即反映
- スピード感のある運用体制
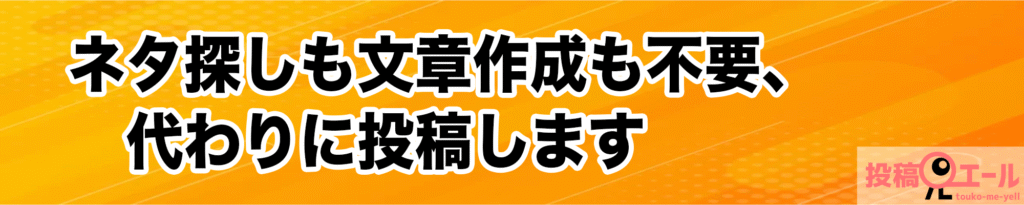
「フォロワーが増える投稿」を再現するために
フォロワーが増える投稿には、いくつかの共通した要素があります。他社の成功事例を分析し、自社の強みやトレンドをうまく取り入れながら、再現性の高い運用を目指しましょう。また、運用代行に頼りきるのではなく、内製化と見える化を進めることで、継続的な成果につなげることができます。ここでは、フォロワー増加を実現するための具体的なポイントを解説します。
- 成功事例の共通点を分析
- 自社らしさとトレンドの両立
- 内製化と運用の見える化
フォロワーが急増している企業アカウントの多くは、「共感設計」が徹底されています。ユーザーの悩みや日常に寄り添うストーリー、リアルな声や体験談、時には失敗談も交えた投稿が共感を呼び、拡散や保存につながっています。また、ユーザー参加型の企画やアンケート、コメントを促す問いかけも効果的です。共感を生む投稿は、アルゴリズムにも好まれやすく、自然なフォロワー増加を実現します。
- ユーザーの悩みに寄り添う
- リアルな体験談やストーリーを発信
- 参加型・双方向の企画を実施
トレンドを追いかけるだけでは、他社との差別化が難しくなります。自社のブランドカラーや世界観、独自の切り口を大切にしつつ、トレンド要素をうまく取り入れることが重要です。例えば、流行のフォーマットや音源を使いながらも、自社のストーリーや価値観を盛り込むことで、オリジナリティのある投稿が生まれます。トレンドと自社らしさのバランスを意識しましょう。
- ブランドカラーや世界観を統一
- トレンド要素を自社流にアレンジ
- 独自の切り口で差別化
運用代行に頼りきると、ノウハウが社内に蓄積されず、改善サイクルも回りにくくなります。自社で運用を内製化し、投稿や分析のプロセスを「見える化」することで、チーム全体のスキルアップと継続的な成果につながります。運用マニュアルやガイドラインを整備し、誰でも運用できる体制を作ることが大切です。また、定期的な勉強会や情報共有も効果的です。
- 運用ノウハウを社内に蓄積
- 投稿・分析プロセスの見える化
- マニュアル・ガイドラインの整備
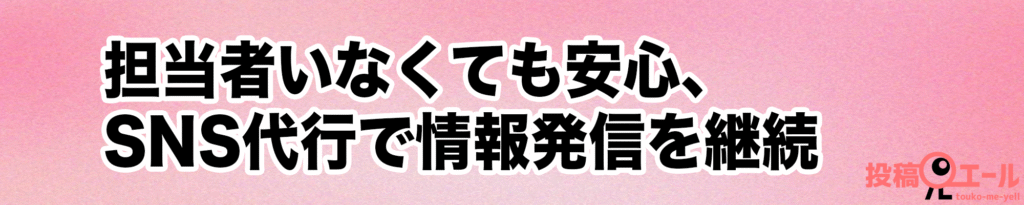
まとめ
SNSでフォロワーが増えない原因は、アルゴリズムの変化やユーザー行動の多様化、運用体制や指標の選定ミスなど、さまざまな要素が絡み合っています。本記事で紹介した“7つの落とし穴”やSNSごとの伸び悩みポイント、改善プロセスを参考に、自社アカウントの運用を見直してみましょう。「質」と「信頼」を重視した運用、目的に合ったKPI設計、チームでの継続的な改善が、これからのSNS運用で成果を出すためのカギです。ぜひ、明日からの運用に役立ててください。
よくある質問(FAQ)
企業SNSのフォロワーが増えにくくなっているのはなぜですか?
投稿頻度を上げてもフォロワーが増えないのはなぜですか?
ハッシュタグをたくさん付けても効果がないのはなぜですか?
SNS投稿の最適な時間帯はいつですか?
企業SNSで成果を上げるために何を改善すべきですか?